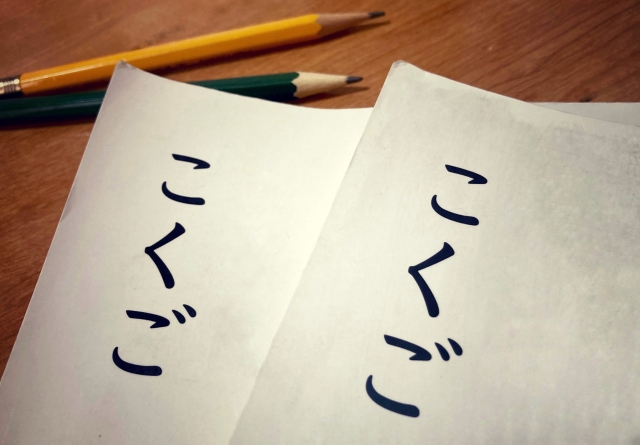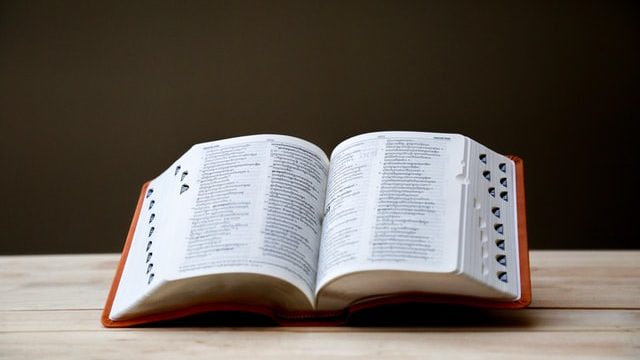こんにちは。
本日は、このブログのタイトルにもあるように、
私のモットー「国語を鍛えれば、大学入試の勝算が劇的に上がる」について説明したいと思います。
なぜ国語なのか?
結論から言えば、国語が思考言語を対象とした学問領域であり、この点において根本的に他の教科と質が異なるものである、と考えているからです。
以下、わかりやすく説明していきます。
すべての教科の土台となる国語
国語はすべての教科の土台である。
みなさんもこの表現を聞いたことがあるかもしれません。
これは実際その通りなのですが、なぜそう言われるのでしょうか。
それは、
私たちは言葉を使って考えており、その言葉を扱う教科が国語であるからです。
英語だって、言葉じゃないですか。と思いかもしれません。
その通りです。
しかし、日本語のネイティブである私たちは、頭の中で考える時は日本語で考えています。
英語ネイティブのアメリカやイギリスの人は頭の中で考える時は英語で考えています。
(なので、言語の文法が国民性を反映していたりと言ったお話もあるのですが、それは話がそれるのでやめておきます。)
つまり、たとえ英語であっても問題を解く時は少なからず日本語で考えています。
私たちは日本人として生まれた以上、この日本語思考回路から抜け出すことはできません。
これが国語がすべての教科の土台であると言われるゆえんです。
この前提をおさえることで、なぜ国語が重要かがわかってきます。
国語を鍛えることで思考力が上がる
つまり、こういうことです。
私たちは言葉を使って考えている
↓
国語は言葉を対象とする教科である
↓
国語を鍛えれば、思考力がUPする。
よく「地頭がいい」という表現が使われます。
テストの点数はあんまりだけど賢い、というタイプのことを指して言われたりします。
私は言語運用能力が高いということだと解釈しています。
「その人と話してみると、その人が賢いかどうかが何となく分かる」とかもこのあたりの事情が関係していると思います。
言われてみれば当然ですが、数学にせよ地歴にせよ、すべて問題文は日本語で書かれています。
つまり、問題文が何を意味しているのかをきちんと読み取り、理解できれば、どのように問題を解けばよいのかもわかってくるわけです。
もちろん、それぞれの教科の専門知識がなければ問題に正解することはできません。
しかし、問題文の指示をしっかりと理解するという段階までは国語でカバーできます。
国語を鍛えるとはどういうことか
ここまでで、国語が思考の土台である言語に直接アプローチする教科であることを説明してきました。
とはいえ、「国語を鍛える」といってもイマイチ漠然とし過ぎていますね。
具体的には、国語を鍛えるとはどういうことでしょうか。
これは古文単語を覚えるとか、漢文の句法を暗記するとか、という話ではありません。
私が「国語を鍛える」という時、以下の点を念頭に置いています。
① 論理
② 文脈
③ 語彙
④ 想像力
です。
順番に説明します。
① 論理
私たち人間には、不思議とものごとの原因と結果を結びつけることのできる力を持っています。
これが「因果関係」という論理です。
論理は(すべての言語を調べたわけではないので分かりませんが)ほぼどの言語にも存在し、人間が世界を認識する時に自然と用いている枠組み※です。
※近代ドイツの哲学者イマヌエル=カントはこれを「ア・プリオリな認識の枠組み」であると述べています。ア・プリオリは「経験に先立って」の意味。
このように、論理というのは私たちがほぼ無意識に使っているものです。
この論理を意識的に捉え直しているのが現代文の問題というわけです。
私たちは、日常会話ではそこそこ論理的に話すことができているのに、書かれた文章になると途端に論理を理解したり、論理的に書いたりすることが難しくなります。
これをなんとかしていこうというのが「国語を鍛える」の一つ目の意味です。
② 文脈
突然ですが、「馬鹿」という言葉はどのような意味でしょうか。
辞書的には「頭が悪いこと」です。笑
「馬鹿にするな!」とか「馬鹿ばっかりだな!」みたいに使います。
では、次のケースはどうでしょうか。
気になっている男の子から、褒められた女の子が
「ばばば、ばっかじゃないの!!」
と思わず言いました。
さて、
これは明らかに「頭が悪い」の意味ではありません。笑
むしろ、マイナスではなくプラスの意味ですらあります。
これが文脈です。
文脈を意識しなければ、単語の意味が分かっても、その文章を書いた人の意図が全く理解できないということにもなりかねません。
入試問題では時々「皮肉」について指摘する問題が出ます。
「皮肉とあるが、どういう点で皮肉なのか」という感じです。
皮肉とは、まさに文脈の中で成立する高度なコミュニケーションであり、なんとなく分かるんだけど、それを改めて指摘することがけっこう難しいのです。
ちなみに、この文脈の力がつくと、モテます。
③ 語彙
まじめな話、やはり漢字や言葉を知っていることは大切です。
たまに、現代文の勉強で漢字や現代文キーワードに取り組まないという方がいるのですが、申し訳ありませんが無謀と言わざるを得ません。
日本人だからと言って、現代文に出てくる語彙を全て理解できるかと言えばそんなことはありません。
そして、普段何気なく使ったり見聞きしている慣用句、その意味を間違って理解しているといったケースも少なくありません。
また、言葉には単なる辞書的な意味だけではなく、「その言葉が用いられる時の世界観」みたいなところまでを含めて理解しておく必要があります。
例えば、「理性」という言葉。
これは、一般的には「感情に判断されず、冷静に判断する能力」といった意味で用いられますが、人類の歴史の中で、この「理性」という概念はかなりの意味の広がりを持っています。
「理性」を神の位置にまで崇拝し、ポジティブに捉えていた時期もあれば、反対に「理性」を2度の世界大戦を引き起こした暴力の原因だとネガティブに捉える時期もあります。
そして、現代文の文章は、こうした言葉についている「匂い」みたいなものを含めて、話が展開していきます。
これを知っているのと知らないのとでは、理解度に天と地ほどの差ができてしまうのは仕方のないことだと言えます。
④ 想像力
最後は、想像力です。
簡単に言ってしまえば、文章を読んで、その内容を絵や写真としてイメージすることができるかということです。
私は、言葉を理解すると言うことは、単にその言葉の意味が分かるだけではなく、その内容が表している世界をイメージできるということだと思っています。
そして、これはけっこう難しいことなのです。
同じ言葉を聞いても、人によってイメージのずれがあります。
だから、ラインやSNSのやりとりで揉めることがあるし、そんなつもりで言ったのではない一言で相手のことを傷つけてしまうことがある。
なんか道徳の話になってきましたが、想像力とはつまるところ、
他人の主張や考えにどれだけ想いを馳せることができるかということであり、
すごくありきたりな言葉を使えば「思いやり」が求められているのです。
もちろん、相手の考えに賛成するしないの自由はあります。
しかし、それ以前にいったんその意見を理解し、受け止めようとする。
私は、国語の学習を通して、この力を育てることができると信じています。
まとめ
最後は少しスケールの大きな話になってしまいましたが、私が国語を極めることを推奨しているのは上記の理由からです。
まとめると次のようになります。
・人間は言葉で考える。だから言葉を扱う国語ができれば、思考力が上がる。
・数学や社会、理科なども、問題はすべて「言葉」で作られている。
・国語を極めるとは、①論理、②文脈、③語彙、④想像力を鍛えていくということ。
月並みな言い方ではありますが、
国語によって身に付く力は大学入試という狭い世界にとどまるものではありません。
一生もののスキルであり、上限はありません。
ぜひ、国語という教科を通して、その最初の一歩を踏み出してほしいなと思います。
今日も最後まで読んでいただきありがとうございました。