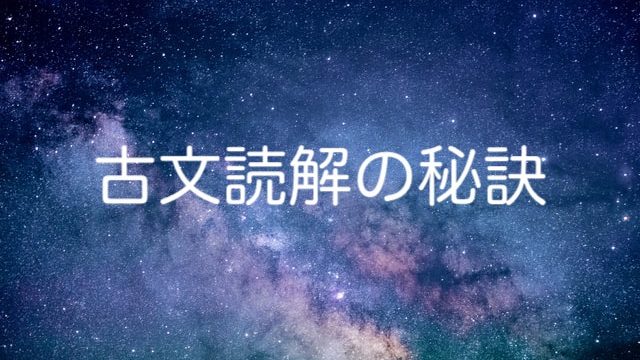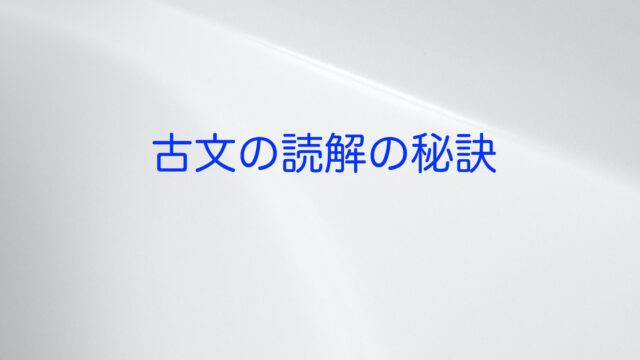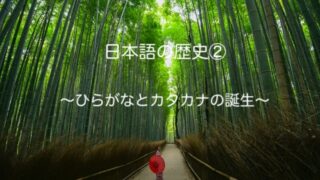今日はちょっと話題を変えて、日本語の歴史について考えてみようか。
日本語の歴史??
うん。
アニメの世界的な流行などによって、日本語を勉強する外国人も増えてきているね。
僕も昨年アメリカ〜メキシコを旅行したんだけど、
日本語を勉強しているという若者に何人か会ったよ。
え、先生いつの間に旅行行ってたの!?(さらっと自慢してきた??)
でも彼ら、彼女らが口を揃えて
「日本語はむずかしい」
って言ってたんだ。
そうかな〜。
私には英語とかの方が断然むずかしいけど。。
そうだね。
でもよく考えてみれば、日本語って不思議な言語じゃないかな?
・ひらがな
・カタカナ
・漢字
・romazi(ローマ字:アルファベット)
と複数の文字体系を組み合わせて使っているよね。
あ、ほんとだ!
英語ってアルファベットしか使ってないかも。
さて、どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。
今日は、そのあたりの話をしたいと思います。
おお、ちょっと興味あるかも!
※今日の内容は大学での国語学の授業で得た知見や、
岩波新書『日本語の歴史』(山口仲美)を参考文献として書いています。
日本は固有の文字を持っていなかった
じゃ、まずは日本の古代にさかのぼるよ。
古代?とは・・?
だいたい弥生時代くらいかな。
ひみこさんの時代だ!
今でこそ、僕たちは複数の文字を「日本語」として使用しているけど、
もともとこの日本列島に住んでいた人々は固有の文字を持っていなかったんだ。
え!?
じゃ、みんな無言で暮らしてたの?
それかウホウホって言ってたとか?(どっちも怖い・・)
葵さん、
言語と文字って似ているようで違うよね。
言語と文字??
・・・
あ、ほんとだ。
うん。
まあ学問的な定義はあるんだけど、
とりあえず
言語=話し言葉
文字=書き言葉
と考えてもらって大丈夫だと思う。
つまり、私たち日本人の祖先は、
話し言葉はあったけれど、書き言葉がなかったということです。
そっかあ〜。よかった〜。
とはいえ、文字がないといろいろ困るよ。
この辺については現代文でも扱われることが多いんだけど、今日はちょっと時間の都合でまた今度話します。
でも、私たちは今こうやって文字を使ってるじゃん。
どうしてこうなったんですか?
うん。
文字を使えるようにするためには、方法は2つだ。
1)自分たちで新しい文字を作る
2)すでに存在している文字を導入する
のどちらかを行う必要があるのだけど、
日本人は2)の道を進んでいきました。
すでに存在していた文字??
あ、わかった!
漢字だ!
さすが、鋭いね。
ちょうど海の向こうには、中国文明という先進国が存在しており、
そこで用いられていた漢字が日本へと伝わっていきました。
輸入文字「漢字」
2通りの読み方
より厳密には、
中国というよりは朝鮮半島からの渡来人によって、
漢字が日本に入ってきたとされています。
日本人たちは、こうした輸入した漢字に
もともと日本で話していた言葉を当てはめていったんだ。
例えば、
外に出て、周りを見るとそこには「ヤマ」があります。
なんでカタカナなの?
メタ発言ありがとう。
当時は文字がないから、とりあえずそう呼んでいたという音を示しています。
なるほど。
それで、
中国でも同じ「ヤマ」を指す文字として「山」があります。
よって、日本語の「ヤマ」を「山」という文字で表すことにしました。
こうして、音と文字が一致し、文字で日本語を表現できるようになっていったというわけだね。
ミズ→水
アメ→雨
みたいな感じ?(カタカナ使ってみた)
うん。
そんな感じ。
そして、そう考えると、面白いことが起きる。
例えば、先ほどの「山」は
①ヤマ とも読めますし、
②サン とも読めます。
①の読み方は僕たちがもともとそう呼んでいたもので、
②は何か分かる?
中国での読み方ってわけね。
あ!
これってもしかして・・・
もう分かったね。
これが音読み、訓読みの原型なんだ。
音読みというのは、もともと中国で読まれていた読み方のことであり、
反対に訓読みとは、日本語としてもともと存在していた読み方ということです。
へぇ〜〜、面白い!
文法と文字の不一致
さて、こうして文字が使えるようになったわけなんだけど、
輸入した文字なので困ったことが起きてきます。
当然ながら、
漢字とは中国語に対応するようにつくられているので、
文法を前提として文字が作られています。
うん?
どういうことですか?
例えば、漢文で「置き字」って習ったよね。
はい。
あの読まないやつですよね?
そう、それ。
でもあの文字は中国語としては読むし、文法的に必要な文字なんだ。
じゃあ、どうして私たちは読まないの??
そこが、言語の違いというやつなんだ。
置き字はその文字によって文構造を説明しているんだけど、
日本語では文構造を説明するためには助詞を使うから、
置き字は日本語に直した時に、役割を失ってしまうんだ。
分かるような、分からないような・・
本来、言語と文字というのはセットで存在していて、
それぞれが対応するようにできている。
でも、
日本はもともと言語(話し言葉)があって、
後から漢字(文字)を輸入したから、
ちょっと不具合が起きてしまうってイメージと言えばいいかな。
完全にぴったりと一致するってわけじゃなくて、
ところどころ噛み合わないみたいな?
そう!
まさにそんな感じだね。
それで、
問題になったのがまさにその「助詞」なんだ。
助詞を表現する漢字が存在しない
順番に説明するね。
まず、中国語の文法は英語に似ていると言われていて、
語順が決まっているんだ。
語順って、
SVOとかSVOCみたいなやつだっけ?
その通り。
だから、
漢字が
吾 日 三 省 吾 身
と並んでいたとすると、
その順番や位置で、主語や動詞、目的語などが分かるようになっている。
なるほど、、
確かに英語に似ていると言われればそうかも。
でも、日本語は語順というものが比較的ゆるくて、
要素を入れ替えても言いたいことを伝えることができる。
そして、それを可能にしているのが「助詞」なんだ。
で、ここで問題になるのが、
日本語の助詞に相当する漢字がそもそも存在しないということだ。
ん〜、
ちょっと難しいぞ。。
分かりやすく並べてみるね。
私は山を見る。
これを漢字で表記すると、、
私 山 見
が残る。
だから、「は」や「を」といった助詞が文字にできないんだ。
うわ、本当だ。
これ、けっこうやばいんじゃ。。
万葉仮名の発明
これ、どうするんですか?
これじゃ私たちは単語で会話しないといけないじゃないですか。
私 家 帰る アイス 食べる
みたいな!
当時の人たちはどうしたかというと、
漢字の意味は無視して、その音を採用したんだ。
例えば、もともと存在していた
「乃」「仁」「於」という漢字の読み方(音)を採用して、
・「〜の」→「乃」
・「〜に」→「仁」
・「〜を」→「於」
と助詞をすべて漢字で表記することにしたんだね。
ああ〜〜、なるほど。
ちなみに「見(る)」などの送り仮名の問題もこれで一応解決したんだ。
暴走族の「夜露死苦」なんかも発想はそれと同じだね。
当て字ってことですね。
こうして、日本語の音に対応するように漢字が採用され、
とりあえず日本語をすべて文字にすることができるようになった。
日本最古の和歌集と呼ばれる『万葉集』は、すべて漢字で書かれているんだ。
だから、こうしてできた文字を「万葉仮名」と言います。
めでたしめでたし〜〜
まとめ
① 古来、日本には文字はなかったが、朝鮮半島から漢字を導入した
② そのため、一つの漢字に1)日本語読みである訓読みと2)中国語読みである音読みの2つが存在する。
③ 漢字は輸入した文字であるため、日本語の文法に完全には対応していなかった。(助詞や送り仮名などに相当する漢字が存在しない)
④ 漢字の「音」だけを採用して、日本語をすべて漢字で表記できるようにした。
→万葉仮名の発明
まあ、すべて文字で表現できるようになったのはいいのかもしれないけど。。
けど、どうしたの?
なんか、全部漢字で書くのダルくないですか?笑
・・・
ああ、ごめんなさい!
何でもないです〜〜
いや、葵さん。
さすがだよ。
まさにそうやって、日本語の歴史は進歩していったんだ。
ええ〜
そうなんですか!?
うん、
じゃ次回はその話をしようか。
次回につづく→【日本語の歴史②】利便を追求した果てに生まれた文字
参考文献:岩波新書『日本語の歴史』(山口仲美)
↑詳しく知りたい方はこちらを実際に読んでみてください。
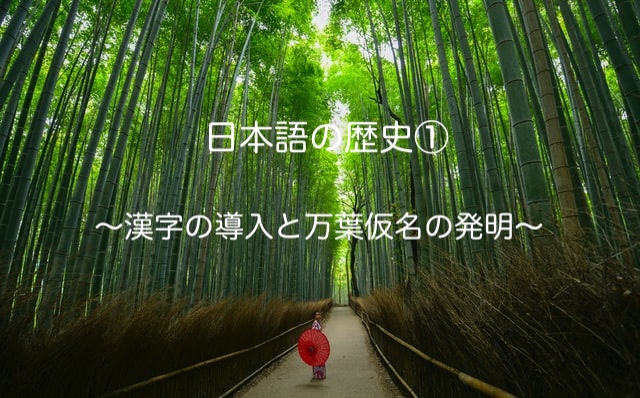
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)