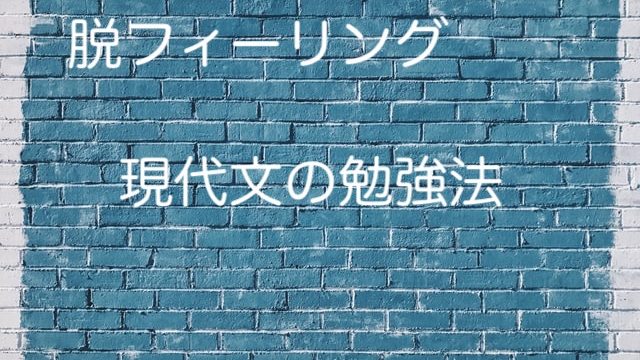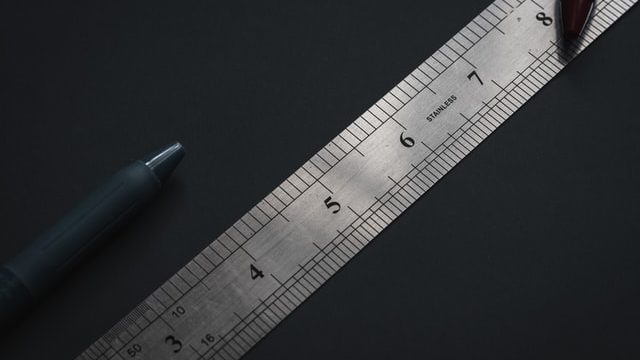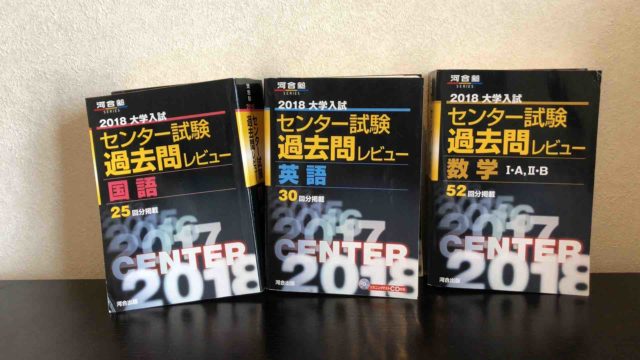現代文の勉強の仕方が分からないという疑問は多いです。
それはおそらく、具体的な「覚える(暗記する)べき対象」のようなものがないからだと思います。
英語なら英単語や文法、イディオムなど、
数学なら公式や解法、問題のパターンなど、
これを覚えていけば、点数に直結すると言うものがあるのですが、
現代文になるといまいちピンとこない。
強いて言うならば漢字や現代文単語くらいですが、これらも(なぜか)英単語や古文単語と比べると、かなりないがしろにされている感が否めません。
そう、お気づきのように、
現代文の勉強は「何かを暗記していく」ことではなく、
どのような点に気を付けて文章を読むのか、その「着眼点」を鍛えるトレーニングだと言えます。
これらを参考書では
・フレームワーク
・解法
・オキテ
などといった言い方で表現しているのですが、本質は同じです。
本日はその着眼点の中でも、最も重要と言われる「言い換え」について紹介していきます。
試験問題の半分は「言い換え」の問題である
現代文の問題の大半は、
「次の文章を読んで、問に答えなさい」
という指示から始まります。
そして、文章にはところどころに線が引かれており、その線に関連した問題が出題されるという形になっています。
さて、少し現代文の問題を思い出してみてください。
設問には「〜〜とあるが、それはどういうことか。」という形の問題が非常に多いということに気づきませんか。
この「どういうことか」という質問。
これは言い換えれば、次のような意味になります。
傍線部には、そのまま読んだだけでは意味が分からないところがあるので、それをみんなが分かるような内容に言い換えてください。
これが分かれば、この「どういうことか」系の問題の解き方がはっきり見えてきます。
<解き方>
① まずは傍線部に「言い換えるべき言葉や表現」がないかを探す。
→言い換えるべき言葉や表現とは、1)難しい言葉や熟語、2)例え、3)筆者がオリジナルの意味で使っている言葉、4)慣用句などです。
② それを言い換えている言葉や表現を傍線部の前後から探す。
→この時、接続語や指示語がどこを探すとよいかのヒントになるので、注目するとよいでしょう。
③ 本文に線を引くなどして、どことどこが言い換えになっているのかを確かめる
④ 内容を理解し、自分が想定した答えに一番近い選択肢を選ぶ
※「選択肢を見る→答えを選ぶ」ではありません。
「答えを自分で考える→それに一番近い選択肢を選ぶ」の順番。
つまり、現代文の勉強で求められているものは、
①何を言い換えを探す、②どこが言い換えなのかを探す、③どれが自分の答えに近いのか選択肢を探す、
といった「探す」スキルだということになります。
なぜ「言い換え」の問題が多いのか
先ほど、現代文の問題の半分以上が「言い換え問題」であると述べましたが、それではなぜそれだけ多くの問題が「言い換え」を要求しているのでしょうか。
答えは簡単です。
文章はほとんどが言い換えでできているからです。
これは、そもそも人はなぜ文章を書くのかを考えると分かってきます。
人はなぜ文章を書くのでしょうか。
ちょっとスクロールを止めて考えてみてください。
はい。
自分の考えを伝えたいからです。
もっと簡単に言えば、
分かってほしいんです。
だから、分かってもらえるように書く工夫をします。
もう分かりますね。
分かってもらうための工夫=言い換え
というわけです。
筆者は自分の分かってほしいところを何度も言い換えて、いろいろな表現で読者に伝えようとします。
ある表現では理解できなかった人でも、別の言い方をされればすんなりと入ってくるということはよくあります。
なので、内容としてはほとんど同じことを言っているんだけど、いろいろな言い方をしているということが少なくありません。
そして、
何度も言い換えると言うことはそれだけわかってほしい部分である
つまり
言い換え=文章における重要な部分である
ということが多いと言うことになります。
現代文の試験とは、当然ながら文章の理解度を問うための試験なので、
文章を理解しているかを問うためには、その「言い換え」にきちんと気づいているかを問題にすればいい
という結論に至ります。
なので、自然と現代文の問題には「言い換え」系問題が多くなってしまいます。
完全なるイコールとは限らない
ただし、一つ注意しなければならないのが、言い換えたものをすべてイコールで繋げることができるかと言われれば、それは慎重になる必要があります。
例えば、言い換えのテクニックとして有名なものとして
「〇〇は△△である」の〇〇と△△はイコールである。
というものがあります。
これ自体は別に間違ったものではなく、むしろ知っておくととても役に立つテクニックです。
しかし、〇〇=△△かと言われれば、必ずしもそうだとは言えません。
例えば、「三段論法」として有名な命題があります。
<三段論法>
① ソクラテスは人間である。
② 人間は必ず死ぬ。
③ ソクラテスは必ず死ぬ。
というものです。
これを記号で一般化すれば、
A=B
B=C
A=C
となります。
しかし、これらの要素
「ソクラテス」「人間」「死ぬ」
は同じでしょうか。
同じではありません。
この事情を説明していくと、話が脱線していってしまうのでやめますが、
何が言いたいかと言うと、
テクニックは万能の公式ではないということです。
テクニックだけを機械的にあてはめるとこのような罠に陥ってしまいます。
だから、こうした技はあくまで文章をシンプルに理解するために使うもので、その理解をより正確にするためには、最終的に自分の頭で考えるしかありません。
すごく結論としてありきたりで申し訳ないのですが、
文章をしっかり読もうぜ
ということです。笑
そして、近年、こうしたタイプの問題が増えてきているように感じます。
とはいえ、この「言い換え」という着眼点を持っていると、文章の理解のしやすさがかなり変わると思います。
最後に、言い換えをつくる表現をまとめておきます。
文章中にこれらの表現が出てきたら「言い換え」かな?と考えるヒントにしてみてください。
<言い換えをつくる表現>
・言い換えれば
・すなわち
・つまり(まとめの意味で使うこともある)
・〜という(同格表現)
<言い換えのパターン>
・熟語↔︎フレーズ
例)示唆している=それとなく伝えている
・熟語↔︎たとえ
例)A帝国はB共和国と国境を接しており、戦力は互角だったが、12世紀になると、A帝国の北の海に海賊が出るようになった。皇帝〇〇はこの「目の上のこぶ」に対処するため・・・ ※ここでは「海賊」が「目の上のこぶ」と言い換えられている