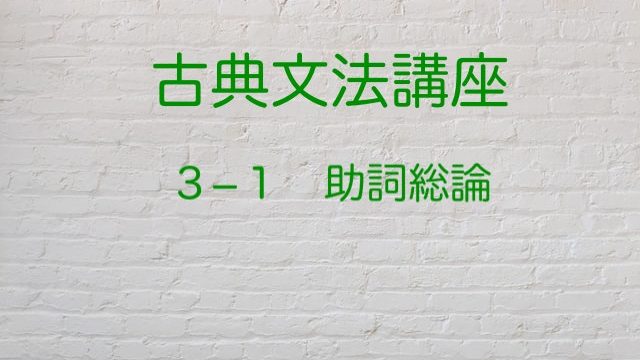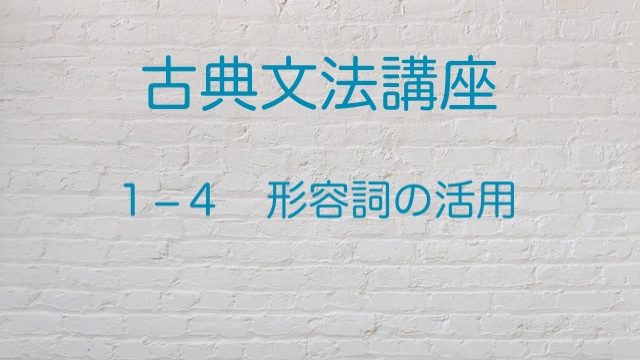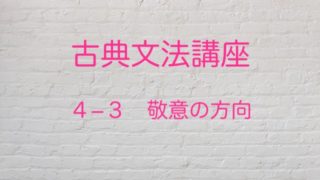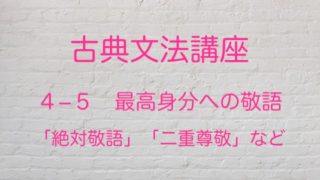浪越考
さて、今日から敬語の応用編に入って行くよ。
ちょっと複雑なところだけど、できるだけ分かりやすく説明していくからよろしくね。
二方向の敬意
浪越考
これまで、尊敬語なら動作の主語、謙譲語なら動作の受け手・・というように敬語を考えてきたね。
→前回:【誰から誰へ?】敬意の方向を解説します
さて、次のケースはどう考えたらいいかな?
例によって、校長先生の例で考えてみよう。
・教頭先生が校長先生のところへ行く。
浪越考
今回は、敬語をあえて使わなかったんだけど、「行く」をどんな敬語で表したらいいかな?
在川葵
えーと、校長先生がえらくて、動作の受け手なんだから謙譲語を使って「参る」?
浪越考
そうだね。でも、教頭先生にも敬語を使わないといけないんじゃない?
浪越考
そうすると、今度は校長先生に敬意を表現できなくなってしまうよ。
在川葵
えー、じゃあどうすればいいの?
まさか、どっちもいっぺんに使うとか?
浪越考
うん。そのまさかだよ。
尊敬語と謙譲語をダブルで使うんだ。
例えば、こんな感じだね。
・中納言(が中宮定子のもとに)参りたまひて、
浪越考
やって来たのは「中納言隆家」といって高貴な身分の人で、来られる側の方も(直接は書かれていないけど)、中宮定子といって身分の高い人だ。
このように動作の主体と客体、両方に敬語を使わなければならないシーンが古文ではよく出てくるんだ。
これを「二方向の敬意」と呼ぶよ。
浪越考
作者からすれば、会話している登場人物が二人とも偉い人であるなら、そのどちらに対しても敬語を使わないといけないからね。
在川葵
ということは、敬語をちゃんと答えるためには、「誰が誰に話しているのか」がちゃんと理解できなきゃダメってこと?
◯二方面の敬意
動作をする人、受ける人どちらにも敬語が必要な場合
→尊敬語、謙譲語を両方重ねて使う
尊敬語、謙譲語に敬意の差はなし
浪越考
さて、このように二方面の敬意をつけるときに気を付けて欲しいのが、「尊敬語と謙譲語の間に敬意の差はない」ということだ。
浪越考
イメージの部分なんだけど、
なんとなく謙譲語より尊敬語の方が敬意レベルが高い感じしない?
尊敬語→かなり偉い人、謙譲語→ふつうの偉い人、みたいに。
浪越考
おそらく「尊敬語→相手を上げる、謙譲語→自分を下げることで相対的に相手を高める」という考えからそう思ってしまうんだと思うけど、尊敬語も謙譲語も同じ程度身分の高い人に使うことができるよ。
在川葵
だから、先生は「その考え方は古文ではちょっと違う」って言ったんだ。
浪越考
うん。
謙譲語の対象として、帝(=天皇)がくることも普通にあるからね。
「尊敬語=動作の主語へ、謙譲語=動作の受け手へ」という定義で覚えておこう。
練習問題
浪越考
さて、実際に二方面の敬意をどのように答えるか考えてみよう。
◯次の下線部の敬語について、1)敬語の種類と、2)誰から誰への敬意かを答えなさい。
1、女御・更衣(帝に)あまたさぶらひたまひける中に、
2、亭子(ていじ)の帝の御供に、太政大臣、大堰(おおゐ)に仕うまつり給へるに、
浪越考
確かに、「さぶらふ」は丁寧語で出てくることも多いけど・・
まず本動詞、補助動詞どっちだろう?
浪越考
OK
本動詞で「さぶらふ」を使うときには、丁寧語になるケースと謙譲語になるケースがあったね。
浪越考
本動詞で丁寧語の場合は「ございます」、謙譲語の場合は「お仕え申し上げる」になるから、どっちが訳して自然かを比べてみよう。
在川葵
んー、「帝に」って来てるんだから、「お仕えする」の方が自然かな。だからこの「さぶらふ」は謙譲語なのね。
浪越考
そういうこと。
「たまふ」はおなじみの尊敬語・補助動詞だね。
次に敬意の方向を考えてみよう。
在川葵
「さぶらふ」は謙譲語だから、動作を受ける方ね。
ということは、お仕えされるほうだから、帝への敬意かな。
在川葵
尊敬語だから、「お仕えする人」、女御・更衣への敬意ね。
浪越考
そうそう、そんな感じ!
2方向の敬意だから、謙譲語の時と尊敬語の時で対象が違っているはずだね。
その調子で2もやってしまおう。
「仕うまつる」は「お仕えする」という意味の謙譲語だよ。
在川葵
ということは、今度も敬意の対象は帝、亭子の帝で・・
そして、そのあとの「給ふ」は、帝じゃない方で、太政大臣への敬意となるわけね。
在川葵
ちょっと時間はかかるけど、解き方、考え方はわかってきたかも!
浪越考
うん、いいね。
2方向の敬意も基本は、前回までに習った敬語と同じだから、落ち着いて考えれば必ずできるよ。
◯答え
1、さぶらふ→謙譲語・本動詞/作者から帝への敬意
たまひ→尊敬語・本動詞/作者から女御・更衣への敬意
2、仕うまつる→謙譲語・本動詞/作者から亭子の帝への敬意
給ふ→尊敬語・補助動詞/作者から太政大臣への敬意
まとめ
・動作をする人、される人どちらも身分の高い人というケースも存在する
・その場合、尊敬語と謙譲語を連続して使う。これを二方向の敬意という。
・それぞれの敬語の答え方は、前回の方法でOK
浪越考
うん、さすがだね。さて、次回はもう少し特殊な敬語のケースを見てみよう。
次はこちら→【絶対敬語と二重尊敬】最高身分への敬意表現を紹介!
◯古典文法講座のホームへもどる
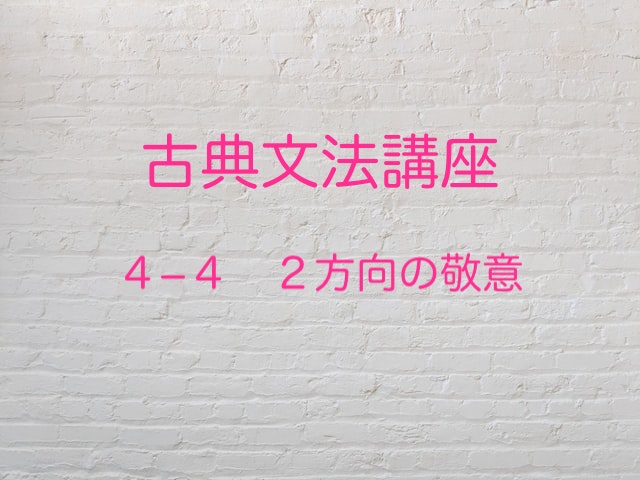
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)